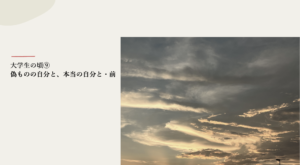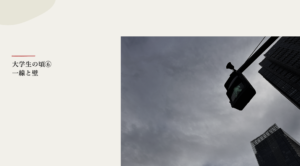高校生の頃にあった話を、思い出しながら。
最初のお話は、こちらから。

蝉の声と夏の匂い
高校生の時、好きだった人がいた。
それは男の子で、僕にとっての初恋とも言えるものだった。
気が付くと彼を探していて、部活中でも放課後でも、偶然会えたりしないかなんて、よく考えていた。
その気持ちが恋だって知ったのは、いつからだろう。
はっきり覚えていない。
確か、蝉の声がけたたましく響く、夏のことだったと思う。
夏の教室で
5階の教室からみる空は、絵具を薄めずにべたっと塗り付けたような青だった。
その青に重ねて、真っ白な雲が、強めのコントラストで浮かんでいる。
それとはまた対象を成すように、教室内は薄暗かった。
じめっとした空気の中で、制汗剤の独特なにおいが鼻をつく。
そこから少しでも逃れるようにして、窓の外をただ眺めていた。
窓から流れる少しぬるめの風でも、あの「シーブリーズ」の強めの匂いを浴びているよりかは、幾分ましだった。
「プールお疲れ様!」
ふいに脇から声をかけられ、意識が教室に戻った。
そこには、体育終わりの彼が立っていた。
「体育、器械運動…だったっけ?」
「そそ、マットなり跳び箱なり。でもこの時期はプールいいよなぁ…暑いもん。」
彼はからは「シーブリーズ」の匂いはしなかった。
(代わりに「ギャッツビー」のにおいがした。)
そこに混ざる彼特有のにおいが、一瞬ふわっとして、
それを「好きだな」と思ってしまった。
「でもプール冷たすぎて寒いよ。」
「じゃあ温めてあげるよ!」
にやにやする彼は、そのまま僕の手をとった。
恥ずかしさとうれしさが相まって、彼の顔から眼をそむけてしまった。
顔をそむけるその一瞬、プール特有の匂いがした。
プール上がりの僕からは、きっとあの塩の匂いがしたに違いない。
生乾きの髪を、早く乾かしたくなった。
「好き」の線引き
「今度さ、俺の地元くる?」
夏休みを迎える前、そんな話になった。
普段学校近くで遊ぶことが多く、誰かの地元で遊ぶということはあまりなかった。
胸が躍った。
彼と二人で遊べる。
それ以上に、彼のことをもう少し知ることができるんじゃないかと思った。
「うん…行く。」
高まる気持ちを抑えながら、そう答えた。
当時の僕は、彼が好きだった。
でも、その好きが、どんな「好き」なのかが分からなかった。
「友達」「親友」「恋人」という三つのカテゴリーはあるけれど、
そのどこに当てはまるかが、分からなくなってしまった。
どこからどこまでが友達で、親友なのか。
そして恋人なのか。その境界が見えなくなった。
線引きが、できなかった。
それも当然だったと思う。
当時の僕は女の子に「恋」をするのが当たり前で、僕もその例外ではなく、
恋愛感情とは女の子にのみ抱くものだとばかり思っていた。
だからこそ、最初は彼と「友達」として仲良くしたいと思った。
もちろん、彼にも他の友達がいる。
彼の事を、僕よりもよく知る友達がたくさん。
その点でいえば、敵いっこなかった。
そんな理由もあって、彼の地元で遊べることが嬉しかった。
少しでも彼のことを知ることができると思ったから。
続きはこちらから。