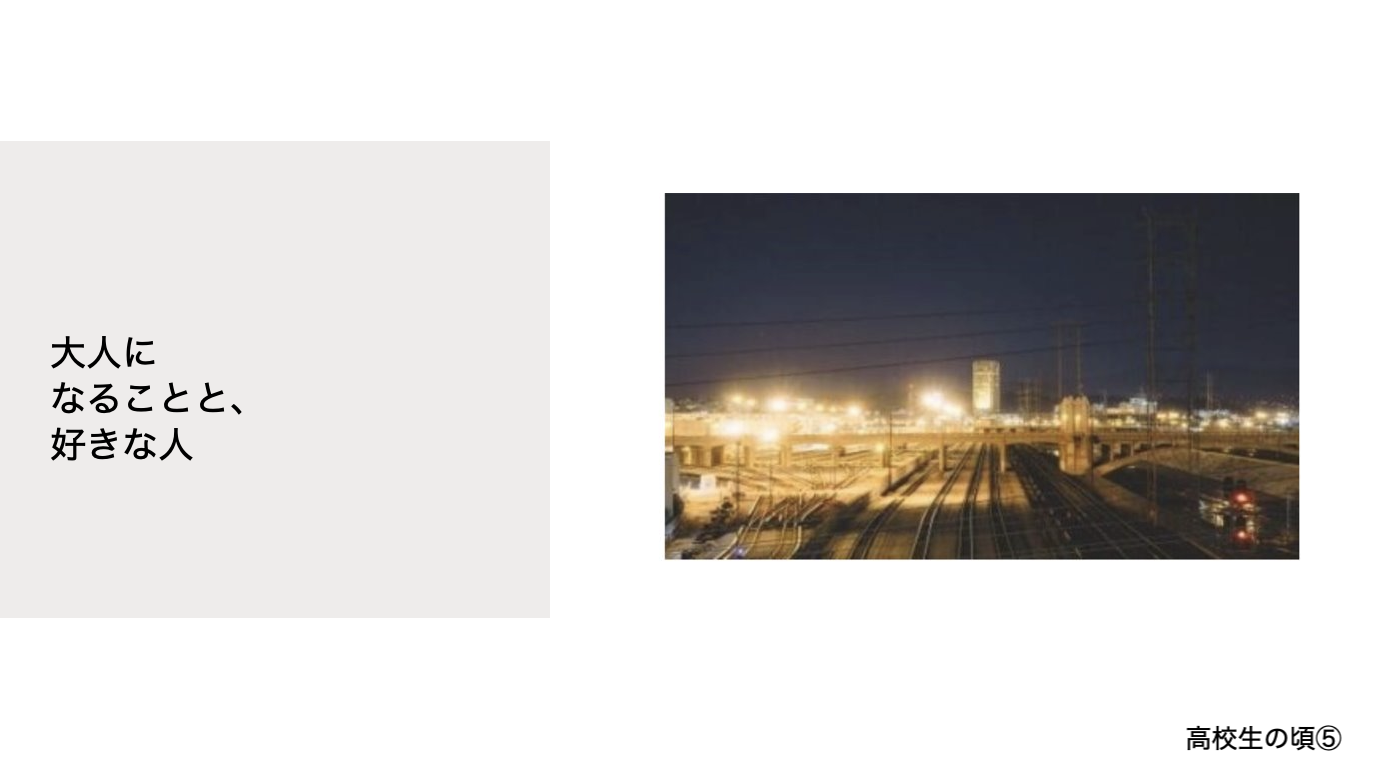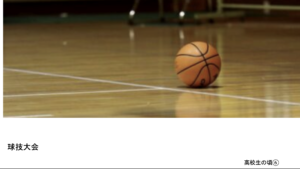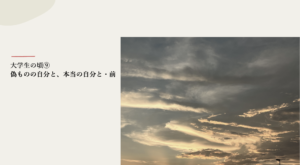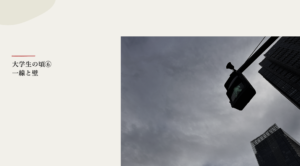今回も高校時代の事を振り返る記事です。5回目。
前回の記事はこちらです。まだ見ていない方は、よかったら。

それでは続きです。
大人になること
思春期特有のものなのだと思う。みんな、どんどん変わっていってしまう。
僕と仲良かった周りの友達も、少しずつではあるけれど「女性」を知っていった。
それが寂しかった。
何も知らない子供だった僕ら。
いつしか異性の誰かを好きになって
付き合って、結婚し、子供を授かり家族になる。
「男」である僕らは、女性を好きになって、そうして大人になっていくんだって
周りの大人から、そう教わった。
周りは徐々にではあるけれど、大人になっていった。
自分だけが置いていかれてしまうような、そんな気がしてならなかった。
みんなと同じように
誰かを好きになったり、付き合ったり、そういう話は僕の周りにはなかった。
ただ学校のみんなは、誰かと付き合うことをステータスのようにしていたし、事実、一か月もしないうちに別れるカップルも多かった。(むしろそっちの方が多かった。)
それでも女の子についての話題が、少しずつ増えていったようにも思える。
僕はみんなと同じ「大人」にはなれないな。
そう、齢16にして悟ってしまった。
ある意味で、僕はみんなよりかは幾分「大人」だったのかもしれない。
自分の行く末が、将来が、みんなとは違うことに気づき
自分自身について、認識し始めたのだから。
〇
「気になってるって、言ってたよ。」
「誰が?」
「Nさん」
最近、その「Nさん」界隈がざわついているのは知っていた。
僕を見てはざわつくのだから、嫌でも気づく。
「少し絡んであげたら?」
「そうだね。そうしてみる。」
こういう少しざわつく雰囲気は嫌いだ。
Nさんと言う子が、僕のことを気になっているらしい。
彼女のことが嫌いなんじゃない。
周りがはやし立て、盛り上げようとする雰囲気が嫌いなのだ。
僕は足早に、教室を後にし、廊下に出る。
休み時間のにぎやかな廊下には、何故だか居場所がないように感じられた。
〇
誰かのことを、好きになろうとして、好きになれるものなのだろうか。
彼女が欲しい。彼氏が欲しい。そんなセリフが耳に入ることも心なしか増えた。
欲しいから探す…そういう考えは理解できなかった。
現に僕は今片思いをしているのだし、これは好きになろうと思って好きになったわけではない。
(そうだとしたら、初めから男なんて好きにならない。)
そう思うからなのか、周りの恋話にはひどく辟易してしまう自分がいた。
好きな人
放課後の嘘
放課後、学校近くのショッピングモールにきた。この日は部活もなく、彼と二人で服を見てまわった。
「Nさんとはどうなの?」
彼が唐突に聞いてきた。彼女の件は、彼も知っている。
「メールしてるだけ。これといって何もないよ。」
「ふーん。いっそのこと女の子と付き合えばいいのに。」
「まぁ…いい人いたらね。」
「好きな人がいるからね。」そう言おうとしたけれど、やめた。
好きな人がいる。そう言った時の彼の反応を見るのが、怖かった。
きっと「だれだれ?」と笑いながら聞いてくる。そんな気がしてならなかった。
そんな彼の顔を、面と向かって見ている自信が無かった。
どうしてか悲観的になってしまう。本当は目の前にいる彼に、好きだと伝えたいのに
今の関係が壊れてしまうのが怖くて、何もできずにいる。
だから、今のまま
「もしかしたら、彼も僕のことを好きになってくれるかもしれない」
という可能性を、残しておきたかった。
「もしかしたら」という可能性の中で、生きていたかった。
「夢」みたいなものだ。いつかは絶対、覚めてしまうことを分かっている。
でも、夢でも見ていないと、きっと自分を保っていられないような気がする。
現実を見ず、なんとか目を覚まさないように。
いつかはそれに、目を向けることになるとしても。
今だけはこのままで……そう願ってやまなかった。
続きはこちらから。